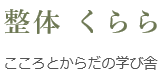私が性被害者となったのは小学5年生。
22歳の頃に初めて自分以外の人に、ほんの少しですが開示しました。それまでは、性被害を打ち明けることはなかった。
どうして誰にも話さなかったのか、私自身もよくわかりませんでした。そもそも幼すぎて何をされていたのかわからなかったですし、わかった時には誰かに話しても拒絶されてしまうのではと思ったり、被害のレベルさえわからなかった。人がどう反応するのか人への恐れがありました。
今、どうして誰にも話さなかったのか、助けを求めなかったのか、知ってほしいと思わなかったのかと振りかえってみると、それは、加害者の相手に対して何も太刀打ちできなかったから。弱さゆえに、小さなからだゆえに、子どもという立場ゆえに、戦うことができないと悟ったんだと思います。周囲や家族や社会に声をあげない選択しかできなかった。傷ついた感情を抑えているほうが楽だった。自分だけ傷ついて、奴隷でいたほうが楽だったんだと思います。誰にもいわないことが一番の身の安全だと思い、言葉も感情も封じていました。何事もなかったかのように日々過ごしていました。
今の日本の国民は、当時の私と同じ状態なのかもしれない。
日本の奴隷、組織の奴隷、何かコミュニティの奴隷など、何も考えず、抗わず、傷ついた感情や、何かに対して湧き上がる感情を出さないほうが、楽なのかもしれません。いちいち反応することで、自分自身が振り回されるのが嫌なのかもしれません。奴隷であることを望んでいるから、日本は消滅していくでしょう。あらゆる分野に外資など民間企業が入り、民営化が進み、一部の人だけがオイシイ思いをし、一般市民はますます貧乏になり、じわじわと搾取され、日本は日本国民のものではなくなっていくのです。ハワイ王国がなくなったように、日本もなくなるでしょう。
日本はハワイになる。国土買収によって失われる未来
財務省・東京都、東京メトロ株を一部売却へ
性被害者の人に対して、「強くなれ」というのは酷なことだと思います。それでも、私は強くありたい。強く生きていきたい。
少しでもそういう強さを国民が持てるのなら、日本はいづれ復活してくるのだと思います。日本の状態や世界の状態を把握すると、絶望しかないのですが、それでも一人ひとりが、できる限りの強さを持って生きていくのなら、この先の日本の姿は変化します。
私が思う強さとは、精神的な強さも含みますが、自分の頭で考え、被害者意識の側に立たず、問題の原因は自分自身にあることを自覚し、自立して納得のいく選択をして、その選択に対して責任を持つ。自分が何者なのかと考え、何のために生きているのかを考え、自分の生き方考え方という思想を持ち、哲学を持って生きていく。混沌とした時代だからこそ、大きな目標を持つ。これが、今私が思う、私にとっての強さの定義です。
整体くららは、2018年10月29日から始まりました。今日は、整体くららが始まって5年です。内海式精神構造分析の師匠、内海聡医師の対応してきた人の数には、まったく及ばないのですが、真剣に、本気で自己の闇に、過去に、幼少や親子関係に向き合い取り組む人には、私も真剣に向き合い取り組みたい。私の今の姿が、見えない生きづらさの原因究明や、根本原因に向き合うために役立てていただけましたら幸いです。無価値だと思っていた自分自身の存在の意義を見い出し、精神的強さを育てることが互いにできればと思います。