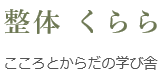2004年。免疫が下がり細菌感染をはじめさまざまな症状が出てきたため、内科や婦人科など精密検査をしましたが、異常なし。出ている症状に対して理由が知りたくて、病名(原因)がほしかったので、最終的に心療内科へ行きました。
結果は「うつ病」
早い段階で抗うつ薬の処方が始まりました。
当時の私に、何をいったら通院も向精神薬もやめれたのか考えることはあります。
病名が与えられたことでホッとしていた自分がいますが、不快な症状の原因がうつ病ではなかったですし、人間関係の問題があったことは確かです。でも、現実をみなかった。
もしかしたら何をいっても無駄だったかもしれない。
精神分析の観点からいえば、闇の計画がすでに働いているので、無駄なことはわかっています。人は見たい現実を自ら作り出す。
でも、もしも、あなたの状態は「ヤク中ジャンキーです」といえば、何か気づきはあったかもしれない。心の病といわれているうつ病。本当に向精神薬を飲み、ヤク中にまでなって、心は治るものなのかと考えたのではないか。
精神の問題は自己の精神でしか治せない。生き方や考え方により人間関係の問題が起き、その問題により苦しんでいるからである。向精神薬で治すという選択は本当に正しいことなのかと、考えるきっかけはいくらでもあったのに、そのきっかけとなったのは、優しい言葉などではない。癒す言葉でもない。
ヤク中ジャンキーに近い言葉だった。
「精神医学とは何か」という答えが私の生き方考え方を変え、私の状態は私が作っていた現実であり、誰のせいでもない。すべては因果応報であり、根本の問題は私の内(内的要因)にあるという現実を突きつけられたことで、ヤク中ジャンキーという現実を直視することができました。
何も言い返す言葉はなかった。愚かとしかいいようがありませんでした。
つらい現実と問題とトラウマなど、今まで避けて見ないようにしてきた自己の精神に直面しなければならないが、命が消えゆく前に、目が覚めてよかった。私にとって向精神薬とは、廃人となり、思考を眠らせる薬でした。